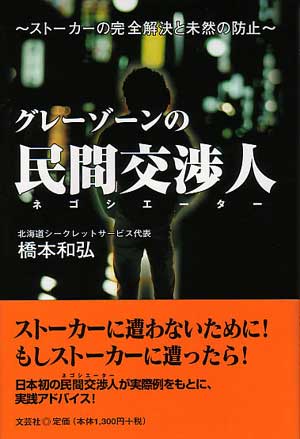 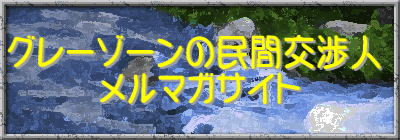 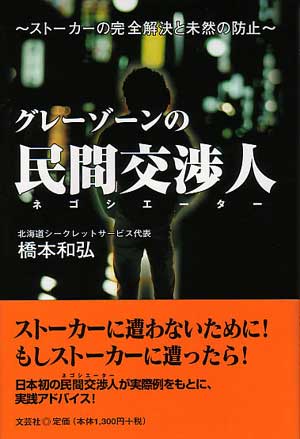
|
||||||||||
|
お探しのものが見つかりませんか? Googleで検索して見て下さい。
|
「ガス事故」と聞くだけで拒否反応を示す私。
パロマは、正直に応えるべき 今回の件とは異なりますが、私の両親は、約6年前に、「ガス爆発事故」で 一遍に亡くなってしまいました。だから、どうしても"人ごと"とは思えない。 【パロマが起こした"CO中毒"】 この「事故」は、なぜ起こったのか?一つ一つの断片を、繋ぎ合わせながら、 出来るだけ、問題の本質に、近づいて行きたいと思います。 パロマ(名古屋市)が事実を隠蔽し、二転三転となった現在までの事故発生件 数は、全国で27件(うち死者20人)、この中で、寒冷地である我が北海道で 起きたのが、半数以上の15件(うち死者9人)もある。 1980(昭和55)年〜1989(平成元年)まで、対象となった7機種の全 国での販売台数は、約26万3千6百台。このうち、北海道内では、2〜3割 が、販売されている。現在も、全国で、約1割程度が使われている(パロマ)。 何故、北海道で多く起きたのか?・・・ 冬でも比較的冷え込みが厳しくない地域では、「室外」に燃焼器を設置する ため、万一、「安全装置」が働かなくても、"CO(一酸化炭素)"は、室外に放 出される。 ところが・・・ 今回、問題となった7機種(PH-81F,PH-82F,PH-101F,PH-102F,PH-131F, PH-132F,PH-161F)は、燃焼器を「室内」に置き、室内の空気を吸気して、室外 に排気する「半密閉式」と呼ばれるタイプで、主に"寒冷地"で使用される。 このため、今回の主原因といわれている「安全装置」が作動しないというこ とは、いったん、COが漏れ出すと、室内に充満し、"命取り"になってしまう 可能性が高い(通常の400倍という高濃度で死亡した例も)。 「安全装置」を作動させなくしたメカニズム・・・ ─────────────────────────────────── 『不正改造』を引き起こすようになった要因として、 「コントロール・ボックス」周辺の故障が、挙げられる。 この故障の報告が・・・ 1993(平成5)年〜1997(平成9)年まで、年間に、約1300件、 報告されている。このうち、1/3が、ボックス内の「はんだ割れ」だった。 「コントロール・ボックス」…排気ファンや、ガス供給を制御する「安全装 置」の役割を持つ。 このため、ボックスの故障で作動しなくなっ た湯沸かし器を使えるようにするため、『不 正改造』が行われるようになった。 「はんだ割れ」というのは、燃焼に伴う湯沸かし器本体の温度差によって、 出来るそうである。だから、北海道のような寒冷地は、温度差が大きいだけ、 比較的温暖なところよりも、「はんだ割れ」を起こしやすいと言える。 ─────────────────────────────────── 『不正改造』の手口は・・・ ─────────────────────────────────── ●「安全装置」の配線を変更 → 排気ファンが回らなくても運転可能 ●「安全装置」の端子を針金で繋ぐ(パロマの講習会にて) → 上記同様 ─────────────────────────────────── 『不正改造』の背景にあるもの・・・ ─────────────────────────────────── ■種火(たねび)が消えるなどの苦情が、多かった。 ■交換用部品の在庫が、なかった。 ■あくまでも、「応急処置」として、行った。 ■古くなった機器は、「安全装置」が働きやすくなってしまう。 ─────────────────────────────────── *つまり、寒冷地にとって、必需品であるガス湯沸かし器を、使えるよ うにするため、『不正改造』を行ったということだ。 ─────────────────────────────────── 『業界』に横たわる問題点・・・ ─────────────────────────────────── ●どの製造会社も、修理用部品は、新製品の販売から数年しか作らない。 ●「安全」を最優先に考えるため、技術革新で、次々と新製品を出す。 このため、旧機種は、修理より、買い替えが、当然という意識が、 他の業界よりも強い。 ●こういった製造会社の旧機種への無関心さが、「事故の情報」を的確に 把握する努力を怠るなど、"対応の遅れ"に繋がった。 ─────────────────────────────────── 『行政』に横たわる問題点・・・ ─────────────────────────────────── ■業界を監視する経済産業省は、「都市ガス」と「LPガス」の事業者を、 管轄する担当課が、異なり、それぞれのガス事業者から、「事故の報告」 を受けた際も、庁内で、連携が取りにくい体制になっていた。 ■1992(平成4)年、旧通産省が、初めて、「制御装置の不正改造」に、 気づいた後も、積極的な原因究明に当たってこなかった。つまり、担当 者自身も言うように、この問題を「ミクロ(どうでもいい)」のものと、 軽く考えていた。 ─────────────────────────────────── 『パロマ』に蔓延る問題点・・・ ─────────────────────────────────── ◆公式な記者会見において「虚偽の事実」を発表した(事故発生件数など)。 ◆実際は、1985(昭和60)年に、最初の事故が発生した段階から、 「全事故」について、発生直後に、全容を把握していた。 ◆その上、1988(昭和63)年には、全国の営業所に『不正改造』を、 禁じる文書も、配布していた。 ◆ある協力業者(パロマ製品の修理、販売を行う)によると、『不正改造』 については、パロマが、年に2〜3回行っていた"講習会"によって、 知ったという証言も、出て来ている。 ─────────────────────────────────── *これに対し、パロマは、説明したことは認めたが、あくまでも、 『不正改造』はやるな、『不正改造』を見つけたら、直ぐに、報告し ろと指導するためのものだったと、釈明している。 ─────────────────────────────────── ◆小林父から小林息子へ、社長が橋渡しされたように、生粋の「同族会社」 である。この弊害が、次の言葉に表れている。「報告を出しにくい環境 が、社内にあったかもしれない」。風通しが良くなかったということ。 ─────────────────────────────────── 主犯のパロマは、もちろんだが、業界全体で、本当に「安全」が最優先され ていたのか?ある意味、「安全が最優先」ではなく、「新製品が最優先」なの ではないだろうか? "浪費社会のツケ"が、この業界に、そして、今回の事故に、如実に表れてい る。日進月歩で、技術や、安全性が高まることは、望ましいことである。 けれど・・・ 1度、新しい湯沸かし器を付けたら、最低でも5年、出来れば10年は持っ て欲しいと思うのが、庶民感覚なのではないか。だから、当然、その位の間は、 交換部品を切らさないするのは、企業として、当たり前のことである。 企業にとっては、多くの消費者の1人かもしれないが、パロマ製品を日々使 っている消費者にとっては、あくまでも「パロマ=自分」という一対一の関係 である。そこには、古い製品、新しい製品などという区分けはない。 この辺のところを、「ガス」という非常にデリケートな物質を扱う機器を作 るメーカーや、関係業者には、今一度、考え直してもらいたい。「安全が最優 先」という言葉は、古いものにも愛着を感じた時に、初めて、出てくる。 もし・・・ コラムを読み、心配になった方は、下記までお問い合わせ下さい。 株式会社パロマ 専用相談窓口 0120−314−552 (いたずら電話はお止め下さい) **一方ではこんな事が・・・→ http://tinyurl.com/khmdt
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Copyright (C) Unlimit Corporation. All Rights Reserved. |
||||||||||